ページに広告が含まれる場合があります。
CPP(Certified Procurement Professional)試験に向けた学習メモとして、今回は「サプライヤー・リレーションシップ・マネジメント(SRM)」についてまとめます。サプライヤーとの関係性をいかに構築・維持・発展させるかは、企業の競争力に直結する重要なテーマです。
サプライヤーとの関係性の重要性
かつては自社内で全てをまかなう「自前主義」が主流でした。
たとえば、フォード自動車のリバールージュ工場は、鉄やガラスの製造まで行う垂直統合型の代表例です。
しかし現在では、サプライヤーから必要な部材やサービスを外部調達するのが一般的です。
外部調達のメリットとデメリット
- メリット:コスト面・技術面での優位性、環境変化への柔軟な対応
- デメリット:コントロール範囲外に依存するため、リスクが増大
このため、外部調達の優位性を維持しつつリスクをどう軽減するかが大きな課題となり、サプライヤーとの関係性マネジメントが重要になります。
サプライヤーとバイヤーの力関係
一見すると、バイヤー企業はサプライヤーを選ぶ立場にあり、交渉力で優位に立てるように見えます。
しかし実際には、
- 特定のサプライヤーに依存している例:
パソコン業界では特定の半導体メーカーやOSの存在が製品戦略を大きく左右することも。
このような場合は、買い手の方が低姿勢を強いられる構造になることもあります。
バイヤーに求められる視点
- サプライヤーは単なる「売り手」ではなく、必要なリソースの供給源
- 信頼関係に基づいた長期的かつ安定した関係構築が不可欠
- 時には新規サプライヤーの開拓も求められる
調達形態と契約の違い
調達品の種類
- 原材料、電気部品、事務用品
- 加工、組立、開発、修理、設置業務 など
調達形態
- 購入:市販されている製品の購入
- 外注:本来自社で行う業務を委託(例:製造、開発、清掃など)
契約の種類
- 売買契約:物品を購入し所有権を移転
- 請負契約:完成責任を伴う業務委託(外注に多い)
※「下請法」の対象外となるケースもあるため、契約形態の理解は重要です。
SRM(Supplier Relationship Management)の導入
CRMとの違い
- CRM:顧客との関係性強化
- SRM:サプライヤーとの関係性強化と調達活動の効率化
サプライヤー関係性マネジメントの方針
方針に含まれる主な項目
- サプライヤーの条件
- 業績の安定性
- 品質・環境・情報セキュリティ管理体制
- CSR・BCP対応
- 取引終了の条件
- 継続取引の終了
- パフォーマンス不良など
- リスク対応
- 供給・CSRリスクへの対応方針
- 不祥事発生時の対応ルール
サプライヤーの分類と戦略
ABC管理
- Aグループ(60%):密な連携が必要
- Bグループ(30%):標準的な管理
- Cグループ(10%):数の削減・手間の軽減
サプライヤーのセグメンテーション
| 分類名 | 調達額 | 代替容易性 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 戦略的関係重視 | 大 | 小 | トップ同士の関係構築がカギ |
| 競合重視 | 大 | 大 | 競争環境を作りより良い条件を追求 |
| 関係重視 | 小 | 大 | 特殊な技術などで小規模でも重要 |
| 効率化重視 | 小 | 小 | 業務効率を最優先 |
サプライヤー管理のPDCA
- Plan(計画):対応方針や発注計画を策定
- Do(実行):実際に調達を行う
- Check(評価):パフォーマンスを評価
- Action(改善):改善依頼や戦略見直しを実施
→ 特に Check(評価)とAction(改善) の強化がポイントです。
関係性構築に向けた具体的な施策
- 戦略方向性の共有
トップ会談や事業説明会の開催 - 早期巻き込み(ESI)
製品企画段階から戦略的サプライヤーを参画させることで、コスト削減・開発期間短縮を図る - CSR対応と影響力発揮
サプライチェーン全体でCSRを徹底
バーチャルコーポレーションという新しい形
従来の垂直統合型から水平分業型への移行が進む中、企業はバーチャルコーポレーション(仮想企業)として、サプライヤーと密接に連携しながら事業を遂行するようになっています。
まとめ
サプライヤーとの関係性の適切な管理は、コストや品質、リスクに直結する重要課題です。しっかりと理解を深めて、試験対策と実務力向上を同時に目指しましょう。
テスト想定
企業形態に関する説明のうち、正しいものを1つ選べ
SRM(Supplier Relationship Management)とは何を目的としたマネジメント手法か。最も適切なものを選べ。

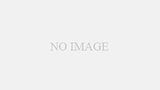
コメント